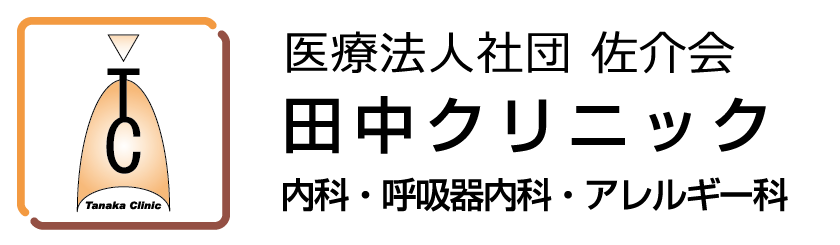睡眠時無呼吸症候群とは、どんな病気なのか? できるだけわかりやすく解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止したり、浅くなったりする病態を指します。
具体的には、睡眠中に口や鼻を通る空気の流れが10秒以上停止する状態を睡眠時無呼吸と定義します。多くの場合、この呼吸停止はいびきを伴います。睡眠時無呼吸症候群と診断されるのは、1時間あたり5回以上無呼吸または低呼吸が発生し、その結果、熟睡感が得られず、日中に過度な眠気を催す場合です。
この疾患は、英語ではSleep Apnea Syndromeと呼ばれ、一般的にSASという略称で知られています。睡眠中に頻繁に呼吸が止まることで、体内に十分な酸素が供給されなくなり、酸素不足の状態に陥ります。このような酸素供給の不足は、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こし、結果として事故のリスクを高める可能性があります。睡眠中の酸素不足は、脳や身体に大きな負担をかけることが知られています。無呼吸と呼吸再開が繰り返されることで、睡眠中にもかかわらず脳が覚醒し、本来休息すべき副交感神経優位の状態から、日中の活動時のような交感神経優位の状態へと切り替わります。この結果、睡眠が浅くなり、夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。
日本国内には、睡眠時無呼吸症候群の患者がおよそ500万人存在すると推定されていますが、実際に適切な治療を受けているのはそのうちのわずか1割程度に過ぎないと言われています。別の報告では、約300万人の患者が存在するとも言われており、いずれにしても多くの患者が適切な治療を受けていない現状があります。この病気は、適切な治療によって症状が劇的に改善することが多いとされています。そのため、正確な診断に基づいた積極的な治療が非常に重要です。
睡眠時無呼吸症候群は、その原因によって大きく2つのタイプに分類されます。一つは、空気の通り道である上気道が物理的に狭くなることで発生する閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)です。もう一つは、脳からの呼吸指令が適切に伝わらなくなることで発生する中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)です。治療の必要性や方法は、これらのタイプや重症度によって異なるため、正確な診断が不可欠です。

睡眠時無呼吸症候群の症状
睡眠時無呼吸症候群の症状は、夜間と日中で異なる様相を呈します。
夜間の主な症状としては、まずいびきが挙げられます。特に、睡眠時無呼吸症候群のいびきは、喉の奥の気道が狭くなることで、呼吸をするたびにその部分が振動するために起こる大きないびきであることが特徴です。慢性的にいびきをかく場合や、朝まで途切れることなくいびきが続く場合、仰向け以外の姿勢で寝るといびきが小さくなる場合、いびきの音が変化して呼吸が止まることがある場合などは注意が必要です。いびきが一旦止まり、その後大きな呼吸とともに再びいびきが始まることもあります。
最も特徴的な症状の一つに、呼吸が止まる、すなわち無呼吸の状態があります。無呼吸とは、10秒以上呼吸が停止している状態を指します。呼吸が乱れたり、息苦しさを感じたりすることもあります。夜間に呼吸が苦しくなる夢を何度も見るという症状も、睡眠時無呼吸症候群が原因となっている可能性があります。息苦しさで目が覚めることもあります。
睡眠中にむせることがあり、これもSASのサインかもしれません。無呼吸によって体が酸素を取り込もうとする際に苦しさからむせることがあります。夜中に何度も目が覚めることも多く、これは無呼吸によって血液中の酸素濃度が低下し、体が危険信号を発するために脳が強制的に目を覚まさせていると考えられています。交感神経が刺激されることで夜間頻尿につながることもあります。これらの夜間の症状は、同居者によって指摘されることが多いのが特徴です。
日中の主な症状としては、まず日中の眠気が挙げられます。日常生活を送る上で支障が出たり、集中力が低下したりすることがあります。仕事中に居眠りをしてしまったり、重要な会議中に眠ってしまうなど、業務に支障をきたすこともあります。特に、自動車の運転中の眠気は非常に危険であり、交通事故を引き起こすリスクが著しく高まります。起床時に体がむくんでしまうこともあります。口が渇いたり、ベタベタしたりする感覚を覚えることもあります。頭痛、特に起床時の頭痛もよく見られる症状です。熟睡感がない、すっきりと起きられない、体が重く感じるなども一般的な症状です。
強い眠気やだるさ、倦怠感が持続することも特徴です。集中力や記憶力の低下も日常生活に影響を及ぼします。その他、不眠、気分の落ち込み(うつ状態)、性格の変化、幻覚、性機能障害なども報告されています。日中の疲れや集中力の低下は、うつ病の症状と類似しているため、SASであることに気づかずうつ病や自律神経失調症と診断される場合もあります。睡眠の質の悪さが感情の整理を妨げ、ストレスを蓄積させ、抑うつ症状を引き起こすという悪循環に陥ることもあります。
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、様々な長期的な健康問題を引き起こす可能性があります。
心筋梗塞や脳卒中を発症する確率が、そうでない人に比べて高いことがわかっています。また、糖尿病を悪化させたり、高血圧や不整脈の原因になったりすることも知られています。
これらの心臓や血管、代謝に関わる病気の発症や悪化に広く関与している可能性が高く、治療せずに放置すると突然死のリスクさえ高まると言われています。AHI(無呼吸低呼吸指数)が中等症以上のSASと診断された場合、高血圧、糖尿病、脂質異常症、冠動脈疾患などの生活習慣病を発症するリスクが、健康な人に比べて2倍以上高まるとされています。閉塞性睡眠時無呼吸症候群を合併した心房細動患者においては、CPAP治療を受けている患者の方が、治療を受けていない患者よりも心房細動の再発率が低いという報告もあります。これらのことから、睡眠時無呼吸症候群の早期発見と適切な治療が、健康維持のために非常に重要であることがわかります。
医療機関への受診の目安
周囲の人からいびきがうるさいと指摘されたり、睡眠中に呼吸が止まっていると言われた場合や睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、早期に医療機関を受診することが重要です。
特に、睡眠時に20秒以上呼吸が止まっている場合は、医療機関を受診する目安となります。ご自身で呼吸停止を確認することが難しい場合は、家族やパートナーに協力してもらい、寝息が聞こえなくなったり、胸の動きが止まったりした際に時間を計ってもらうと良いでしょう。睡眠中にむせて目が覚める場合や、夜中に何度も目が覚めてしまう場合も、医療機関への受診を検討すべきです。
日中の症状も重要な受診の目安となります。強い眠気や倦怠感、集中力の低下などによって日常生活に支障が出ている場合は、医療機関を受診しましょう。起床時に頭痛がしたり、憂鬱な気分が続く場合も、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
いびきは睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状の一つですが、いびきをかく人全てが睡眠時無呼吸症候群であるわけではありません。しかし、慢性的にいびきをかいている人は、睡眠時無呼吸症候群のリスクが高いと考えられます。特に、大きないびきをかいている、いびきが止まって呼吸が止まっていることがあると指摘された場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。
一人暮らしで夜間の状態が把握しにくい場合は、日中の自覚症状に基づいて受診を検討しましょう。日中の強い眠気や集中力の低下、倦怠感など、日常生活に支障がある場合は、医療機関を受診することをお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群の検査と診断
睡眠時無呼吸症候群の診断は、問診から始まり、必要に応じて様々な検査が行われます。
問診では、既往歴や日中の眠気などの症状について詳しく聞かれます。就寝中のいびきの有無や程度、無呼吸の有無など、睡眠時の様子は自分自身では把握しきれないことが多いため、可能であれば、様子を知っている家族やパートナーと一緒に受診することが望ましいです。一人暮らしの場合でも、眠気や集中力の欠如、疲れやすいなどの症状があれば、遠慮せずに受診しましょう。問診に加えて、病的な眠気かどうかを評価するために、睡眠尺度評価(ESS)などの質問票が用いられることがあります。
夜間SPO2検査(PSG検査): これは、睡眠時無呼吸症候群の可能性をスクリーニングするための検査です。パルスオキシメータという装置を用いて、指先にセンサーを取り付け、睡眠中の血液中の酸素の状態と脈拍数を測定します。これにより、無呼吸によって起こる酸素の低下状態を評価することができます。腕に小型の機器を装着して一晩睡眠をとるだけで検査が可能です。自宅で行うことができるため、普段の睡眠に近い状態で検査を受けることができます。

簡易検査(Home Sleep Apnea Testing): 睡眠中の酸素低下が認められる場合には、さらに別の検査機器を使用して、無呼吸が起きているかを検査します。指先だけでなく、鼻の下にセンサーを取り付けて、いびきや呼吸の状態を測定します。この検査では、10秒以上の無呼吸や低呼吸が1時間あたりに何回起こるか(無呼吸低呼吸指数:AHI)や、酸素の低下状態などを測定することができます。
睡眠時無呼吸症候群の治療方法
睡眠時無呼吸症候群の治療法は、その重症度や原因に応じて様々な方法があります。
生活習慣の改善: 肥満はいびきや睡眠時無呼吸の大きな原因の一つです。体重を減らすことで症状が改善する可能性が高いため、食事療法や運動療法による体重管理は重要な治療法となります。また、アルコールは筋肉を弛緩させる作用があり、いびきや無呼吸を引き起こしやすくするため、就寝前の飲酒は避けるべきです。喫煙も気道を狭くする原因となるため、禁煙が推奨されます。睡眠薬は気道を塞がりやすくする可能性があるため、服用している場合は担当医に相談することが重要です。
持続陽圧呼吸療法(CPAP療法): 中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に対する第一選択となる治療法です。睡眠中に、鼻に装着したマスクから適切な圧力をかけた空気を送り込むことで、気道を確保し、無呼吸を防ぎます。CPAP療法は、その安全性と治療効果が国際的にも確認されており、多くの患者が睡眠の質の改善を実感しています。簡易検査でAHIが40回以上、PSG検査でAHIが20回以上の患者には特に推奨されます。前述のAHIの回数が睡眠時無呼吸症候群の診断に用いられていましたが、最近はAHIはREI(呼吸イベントインデックス)という呼び方に変わってきており、REIで5~15以上の軽傷でも、疾患により早期CPAP導入が望ましいケースがあります。
まれに、マスクの装着感などが原因でCPAP療法を継続することが難しい患者もおり、そのような場合には、他の治療法への変更が検討されます。CPAP療法では治療を継続できるよう、患者の治療状況の確認、圧力の調整、マスクの変更、顎固定具の使用などのサポートが行われます。そのために、定期的な通院が必要です。CPAP両方は健康保険が適用されます。
マウスピース(口腔内装置)療法: 軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群に対して用いられる治療法です。睡眠時にマウスピースを装着することで、下あごを前方に固定し、空気の通り道を広げます。簡易検査でAHIが5回以上20回未満の患者に適応となり、マウスピースの作成には健康保険が適用されます。
外科的治療: アデノイドや扁桃肥大が気道閉塞の原因となっている場合など、特定の原因に対しては手術による治療が行われることがあります。特に小児の睡眠時無呼吸症候群では、アデノイドや扁桃の肥大が原因となることが多いです。鼻閉などの鼻疾患がCPAP療法やマウスピース療法の妨げになる場合にも、手術が必要となることがあります。喉の組織を切除して気道を広げる手術もありますが、出血や腫れのリスク、入院が必要となる場合があります。外科的治療は、術後の再発の可能性もあるため、十分な術前評価が必要です。
その他の治療法や考慮事項: 鼻閉による口呼吸が原因でいびきや睡眠時無呼吸症候群が認められる場合には、鼻腔を広げるナスステントの使用が検討されることがあります。また、必要に応じて、栄養士による栄養指導やリハビリテーションが行われることもあります。高度な肥満症の患者に対しては、糖尿病・減量外来と連携して、減量手術が検討されることもあります。
日常生活での注意点と合併症
睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病と密接に関連しています。放置すると、心筋梗塞や脳卒中などの循環器系の病気を発症する危険性が高まることがわかっています。また、糖尿病を悪化させたり、高血圧や不整脈の原因になったりすることも知られています。したがって、睡眠時無呼吸症候群の管理においては、これらの合併症のリスクを考慮した総合的な評価と治療が重要となります。患者一人ひとりの状態に合わせた個別化された治療計画が不可欠です。
睡眠時無呼吸症候群による日中の過度な眠気は、自動車の運転中に眠気を催し、交通事故を引き起こす危険性を著しく高めます。過去には、運転中の事故や鉄道のオーバーランなど、睡眠時無呼吸症候群が関与した事例も報告されており、安全性確保の観点からもこの病気の適切な管理は非常に重要です。
まとめ
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の呼吸障害によって引き起こされる一般的な疾患であり、日中の眠気や倦怠感、集中力低下など、日常生活に様々な影響を及ぼします。重症化すると、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中などの深刻な合併症を引き起こす可能性もあるため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。いびきや呼吸停止などの症状に気づいたら、自己判断せずに専門の医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けることをお勧めします。治療法は、生活習慣の改善からCPAP療法、マウスピース療法、外科的治療まで多岐にわたり、個々の患者の状態や重症度に合わせて選択されます。睡眠時無呼吸症候群を適切に管理することで、生活の質を向上させ、長期的な健康リスクを低減することが期待できます。
医療法人社団佐介会 田中クリニックでは、呼吸器専門医が担当し、睡眠時無呼吸症候群の診断・治療を行っています。気になる症状などがありましたら、是非お気軽にご相談ください。