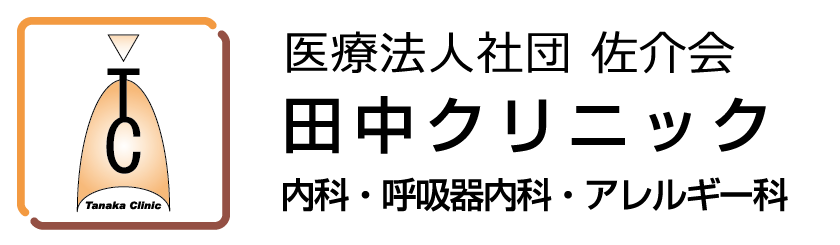気管支喘息とは、どんな病気なのか? できるだけわかりやすく解説します。
気管支喘息とは
気管支喘息は、肺の気道に慢性の炎症が生じる一般的な疾患です。この状態は、気管とその周囲の筋肉の収縮を伴い、空気の通り道が狭くなることで特徴付けられます。
その結果、患者は発作性の息苦しさ、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)、咳、胸の圧迫感などの症状を経験します。
喘息は、気道に持続的な炎症(いわば小さな火事のような状態)があり、様々な刺激に対して気道が過敏になり、発作的に気道が狭くなる(大きな火事のような状態)ことを繰り返す病気と捉えることができます。重要な点として、喘息患者の気道では、症状がない時でも炎症が続いています。この持続的な炎症と修復の繰り返しは、気道の壁を厚くし、気道を硬く狭くしてしまう可能性があり、結果として治療が困難になることがあります。
喘息の発症には、遺伝的要因と環境要因の両方が複雑に関与していると考えられています。日本においては、子供の8〜14%、成人では9〜10%が喘息を患っており、高齢になって初めて発症する人もいます 。
リスク要因としては、大気汚染やアレルゲンが挙げられます。アレルギーは喘息の一般的な原因であり、特に室内アレルゲンであるハウスダストやダニが最も多いとされています。ペットのフケやカビも喘息の引き金となることがあります。
喘息は、胃食道逆流症(GERD)、副鼻腔炎、閉塞性睡眠時無呼吸症候群などの合併症を伴うこともあります。
気管支喘息の症状
気管支喘息の典型的な症状としては、呼吸時に「ゼーゼー、ヒューヒュー」という音がする喘鳴(ぜんめい)、息苦しさ(呼吸困難)、発作性の咳、痰などが挙げられます。これらの症状は、特に夜間から早朝にかけて悪化しやすいことが特徴です。安静にすることで自然に症状が改善することもありますが、多くの場合、治療が必要となります。気道が狭くなることで十分な呼吸ができなくなり、息苦しさを感じる人も少なくありません。
喘息の症状には、喘鳴や呼吸困難が目立たない咳喘息というタイプも存在します。咳喘息では、慢性的に咳が続くことが主な症状であり、「ゼーゼー、ヒューヒュー」といった呼吸音は伴いません。
また、運動誘発喘息のように、特定の状況下でのみ呼吸困難が生じる場合もあります。喘息発作の重症度は様々であり、軽度なものから生命を脅かす重篤なものまであります。
喘息の症状は、風邪や気管支炎と間違われることもありますが、喘息では症状がない時でも気道の炎症が続いている点が異なります。また、心不全でも喘鳴が見られることがあるため、注意が必要です。咳は、胃食道逆流症、副鼻腔炎、閉塞性睡眠時無呼吸症候群など、他の疾患の症状である可能性も考慮する必要があります。

医療機関への受診の目安
喘息の症状が疑われる場合、例えば繰り返す喘鳴、息切れ、持続する咳(特に夜間に悪化する場合や特定の要因で誘発される場合)には、医師の診察を受けることが推奨されます。風邪の症状が治まった後も「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音が残る場合や、季節の変わり目や寒暖差で症状が現れる場合も同様です。風邪を引いた後、2〜3週間以上咳が続く場合、特に夜間や早朝に咳に悩まされている場合は、喘息の可能性を考慮し、医療機関を受診するべきです。
具体的には、以下のような状況が見られた場合には、医療機関への受診を検討してください。睡眠中に咳き込んだり、息苦しさで目が覚めてしまう場合、速効性のある薬(短時間作用性β2刺激薬など)の効果が不十分な場合や、効果がすぐに切れてしまう場合(3時間以内)、普段よりも頻繁に、または重度の発作を経験する場合、発作時に使用する薬がない場合、初めて喘鳴や息切れなどの症状が現れた場合、そして2ヶ月以上続く咳がある場合(他の病気が隠れている可能性もあります)。
特に、以下のような症状が現れた場合は、救急医療機関への受診が必要です。横になれないほどの強い息切れ、唇や指先が青くなる(チアノーゼ)、意識が朦朧とする、または反応がない、強い胸の痛み、そして、普段使用している速効性の薬を使用しても症状が改善しない、または悪化する場合。これらの症状は、重篤な喘息発作を示唆している可能性があり、迅速な対応が求められます。
気管支喘息の診断方法
気管支喘息の診断は、症状、病歴(アレルギーや家族歴を含む)、そして治療への反応に基づいて行われることが多いです。特に、症状の頻度、誘因、時間帯(夜間の出現)などを詳しく問診することが重要です。
呼吸機能検査(スパイロメトリー)は、患者が吸い込んだり吐き出したりできる空気の量と速さを測定する検査です。
呼気中一酸化窒素(FeNO)濃度測定は、呼気中のNOのレベルを測定する検査です。
アレルギー検査(血液検査でIgE抗体を測定)は、ダニ、ペット、花粉、カビなどの特定のアレルゲンに対する反応を確認するために行われます。特定のアレルゲンを避けることが、喘息の悪化予防につながります。
ピークフローメーターは、患者自身が自宅などで最大呼気流量(PEF)を測定するための携帯型デバイスです。定期的なPEFモニタリングは、喘息のコントロール状態を把握し、誘因を特定し、喘息の悪化の早期兆候を検出するのに役立ちます。
その他、喘息と類似した症状を示す他の疾患を除外するために、胸部X線検査が行われることがあります。痰の検査は、気道の炎症を示す好酸球の増加を確認するために行われることがあります 9。これらの多様な診断方法により、喘息の包括的な評価が可能になります。
気管支喘息の治療方法
気管支喘息の治療の主な目標は、症状をコントロールし、喘息の発作を予防し、良好な肺機能を維持することで、正常で活動的な生活を送れるようにすることです。治療は通常、薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせたものです。治療のアプローチは、喘息の重症度に基づいて段階的に行われることが多いです。
長期管理薬(コントローラー)は、気道の炎症を抑え、喘息の症状や発作を予防するために毎日服用する薬です。吸入ステロイド薬(ICS)は、長期管理の基本であり、気道の炎症を効果的に軽減します。長時間作用性β2刺激薬(LABA)は、気道の筋肉を弛緩させ、気管支の収縮を防ぐのに役立ちますが、必ず吸入ステロイド薬と併用されます。抗IgE抗体療法(オマリズマブ)は、他の薬でコントロールできない重症のアレルギー性喘息に使用される注射薬です。その他、特定の炎症経路を標的とした新しい生物学的製剤も、重症喘息の治療に利用可能です。
速効性薬(リリーバー)は、喘息の発作が起きたときに症状を迅速に軽減するために使用されます。短時間作用性β2刺激薬(SABA)は、最も一般的な速効性薬であり、気道の筋肉を迅速に弛緩させ、喘鳴、咳、息切れなどの症状を緩和します。
ICSとLABAを含む配合吸入器は、多くの患者にとって一般的な治療法です。吸入薬を肺に効果的に届けるためには、正しい吸入器の使用法が非常に重要です。医療従事者から適切な指導を受け、定期的に確認することが推奨されます。
喘息の管理には、誘因の特定と回避も重要です。一般的な誘因には、アレルゲン(ダニ、ペットのフケ、花粉、カビ)、刺激物(煙、大気汚染、強い臭い)、冷気、運動、感染症などがあります。室内アレルゲンを減らすための定期的な清掃、禁煙、およびアレルギーやGERDなどの基礎疾患の管理が有益です。運動誘発喘息の場合、運動前のウォーミングアップや予防薬の使用が推奨されることがあります。
医療法人社団佐介会 田中クリニックでは、呼吸器専門医が担当し、気管支喘息の診断・治療を行っています。気になる症状などがありましたら、是非お気軽にご相談ください。